宮本武蔵の活躍をしるした小倉碑文というものがあります。
武蔵の養子・伊織(いおり)が建立した碑です。
そこにどんなことが書いてあるのか、要点をしぼってざっくりと現代語訳してみました。
小倉碑文 ざっくり現代語訳
宮本武蔵はすごい人です。彼は二刀流を生み出しました。
彼のお父さんは、十手(じって)の名人でした。
武蔵もはじめは十手の練習をしていました。
でも…
あるとき、こう考えるようになります。
「たしかに十手は、刀の何倍もすぐれている。でも、十手は刀とちがって、いつも身に付けているものじゃない。それに対して、刀はいつも2本、身に付けている。じゃあ、2本の刀を十手のように使えば、すごく強くなれるじゃないか!」
こうして武蔵は、二刀の使い手になりました。
武蔵は、真剣や木刀を投げて、逃げるものに命中させることもできました。
13歳のときには、播州新当流の有馬喜兵衛という人物と戦って勝ちました。
16歳の春には、但馬国に行き、秋山という人物に勝ちました。これで武蔵は一躍有名になりました。
そのあと武蔵は京都に行き、すごく強いといわれる剣の名門・吉岡ファミリーに決闘を申し込みました。
武蔵はまず、蓮台野で吉岡清十郎に勝ちました。
つぎに、吉岡伝七朗に勝ちました。
吉岡の弟子たちは話し合いました。「剣の腕では武蔵にかなわない。大勢で一気にやっつけよう」
これを知って武蔵は、自分の弟子たちに言いました。
「きみたちは関係のない人間だ。はやく逃げなさい。私ならだいじょうぶ。たとえやつらが群れを成してかかってきても、私から見れば浮雲みたいなものだ。なにも心配いらないよ」
その言葉どおり…
武蔵はたった一人でたくさんの敵をやっつけました。
武蔵の強さに、京都中がおどろきました。
その後、吉岡ファミリーは兵法家をつづけられなくなりました。
ある剣の達人がいました。巌流(がんりゅう)という流派です。
彼が武蔵に言いました。「真剣で勝負しよう」
武蔵は答えました。「きみは真剣でワザの限りを尽くすといい。私は木刀でこの腕前を披露しよう」
長門国と豊前国のあいだに浮かぶ船島で、両者は同時に相対しました。
巌流は、ワザの限りを尽くしました。
が。
武蔵は木刀の一撃で、巌流をたおしました。そのスピードといったら、電光さえも遅いほどです。
武蔵は13歳から壮年まで、60回以上も勝負をして負け知らずでした。すごい人です。
武蔵はつねに言っていました。「兵術をしっかり身につければ、戦場で大軍を動かしたり、国をおさめることも、けっして難しくないだろうね」と。
武蔵は、石田三成の謀反(関ヶ原の戦い)や、秀頼公の乱(大坂の陣)でも活躍しました。
武蔵は、剣だけではなく、礼儀や音楽や弓矢、乗馬、書道、算数、文学も得意でした。
武蔵は、肥後国で亡くなりました。私、伊織はこの碑をたて、武蔵の活躍を後世に残します。
ああ、宮本武蔵。とても偉大な人ですね。
おしまい。
佐々木小次郎の名前はない
以上が、小倉碑文のざっくり現代語訳です。
ここに書かれていることがぜんぶ本当とは限りません。でも、武蔵の死から10年ほどしか経っていない時期につくられたものなので、時期的にはわりと武蔵に近い史料ですよね。
小倉碑文を読むと、「佐々木小次郎」という名前は出てきません。ただ巌流とだけ呼ばれています。
巌流島の決闘も、武蔵が遅れたとは書かれていません。同時に相対した、と書かれています。実際のところ、どうだったんでしょうね。
小倉碑文は武蔵側の人間(武蔵の養子)が残したものですから、巌流島にわざと遅れて行ったことをあえて書かなかったとも考えられますよね。
と。
こんなふうに…
実際はああだったのかな、こうだったのかな、と想像するのって、楽しいですよね~。
遠い歴史のあれこれを想像する。ムフフです。浪漫です。

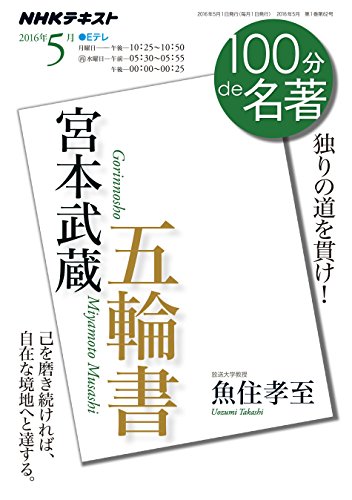

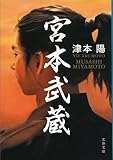



 』で有名な齋藤孝さんの書いた本です。
』で有名な齋藤孝さんの書いた本です。





